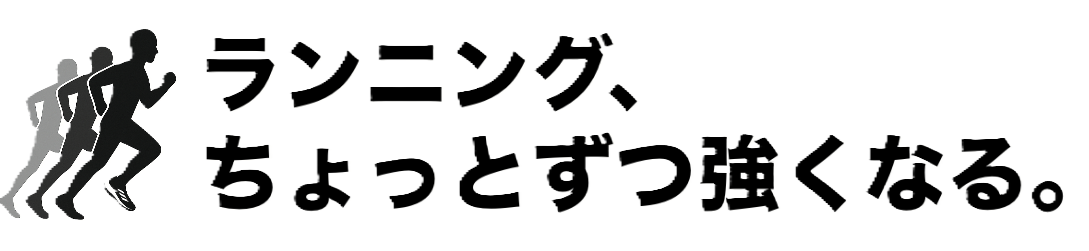マラソン練習は、かつ丼作りに似ている
ふと思ったんです。マラソンの練習って、かつ丼の作り方と似ているなって。
ごはん=ジョグ|地道な積み重ねが8割
まずは、ごはん。これはマラソンにおけるジョグ。週に何度も、何キロも走る地道な積み重ね。全体の8割を占める土台で、これがふっくら炊きあがっていないと、どんな豪華な具材を乗せてもおいしくならない。
ちなみにこのお米を炊く“水”は、シューズ選びにあたると思う。どんな水を使うかでごはんの出来が変わるように、どんなシューズで走るかで足の調子も変わる。自分に合った水(シューズ)を選ぶのは、意外と奥が深い。
とんかつ=スピード練|火加減とタイミングが命
次にとんかつ。これはインターバルやレペティションなどのスピード練習。油の温度が高すぎれば焦げてしまうし、揚げる時間が長すぎても中がパサパサになる。ちょうどいい火加減で、サクッと中はジューシーに。
…そう、まさにスピード練の「負荷」と「時間設定」そのもの。焦りすぎればケガをするし、怖がって温度を上げられなければ、力はつかない。火傷(故障)が起きやすいのも、だいたいこのパート。
そして、揚げ始める“タイミング”もすごく大事。まだごはんが炊けていないのに、とんかつを揚げ始めたらどうなるか?冷めて衣はベチャッとし、肉の旨味も飛んでしまう。つまり、スタミナができていないうちにスピード練習を始めても、効果は薄いしケガのリスクが高い。
だから、ちゃんとごはん(ジョグ)で土台を整えてから、とんかつ(スピード練習)に火を入れる。この順番を守ることが、いいかつ丼には欠かせない。
卵=テンポ走・テーパリング|全体のバランスを整える
そして卵。これはテンポ走やペース走であり、テーパリングでもある。とんかつとごはんをつなぎ、全体のバランスをとる大事な存在。
ここは非常に繊細。火を入れすぎて固まってしまえば「やりすぎ」になり、ピークを越えてしまう。逆に生すぎれば、全体がまとまらない。だから、ここは絶妙な火加減、ちょうどいい半熟=テーパリングが必要になる。
経験と感覚と、小さな調整の積み重ね。マラソンに向けた最終調整は、卵焼きと似ている。
プロのどんぶりと、市民ランナーの器
プロのランナーたちは、たらいのような大きなどんぶりでかつ丼を作る。お米の量も多ければ、カツの厚さも規格外。卵も何個使ってるんだってくらい豪華。そして何より「時間」があるから、理想的なレシピで調理できる。
でも、僕たち市民ランナーは、そこまでの大きなどんぶりは使えない。仕事がある。家庭がある。時間という材料が限られている。
そして、年齢を重ねるごとに、そのどんぶりはだんだん小さくなっていく。20代のころはガッツリ盛れていた具材も、40代になるとだんだん量を減らして、味を引き立て合う方向に。
大盛りにこだわるのではなく、限られた器で、いかに美味しく仕上げるか。それが市民ランナーにとっての腕の見せどころだと思う。
失敗しても、また作ればいい
ちなみに、失敗することもある。米が芯を残していたり、油の温度が合わずカツがベチャッとなったり。卵を入れるタイミングが早すぎて、全体が固まってしまったり。
マラソンで言えば、走り込みが足りなかったり、スピード練習に偏ってしまったり、調整がうまくいかなかったり。
そんなときは、食材や調理法を見直すしかない。でも、失敗してもまた作ればいい。走り終わった後に「今回は少し焦げたな」「火が通りきらなかったな」と思うことがある。それでも、「次はこうしよう」と考える。何度でも、何杯でも、自分のどんぶりは作り直せる。
まとめ:自分だけの“最高の一杯”を作る
僕の理想は、見た目は控えめでも、食べた瞬間に“ちゃんとうまい”と言いたくなるかつ丼。
お米にこだわり(ジョグの質)、カツの種類や揚げ方にこだわり(スピード練の負荷や内容)、卵は絶妙な半熟にして(テーパリング)。
飾りすぎず、盛りすぎず、でも自分で食べて「これだな」と思える一杯。誰かと比べなくてもいい。自分の器の中で、自分の最高を作る。
それが僕の理想のマラソン練習の形なんだと思う。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が「なるほど」「面白い」と思っていただけたら、SNSなどでシェアしていただけると嬉しいです!