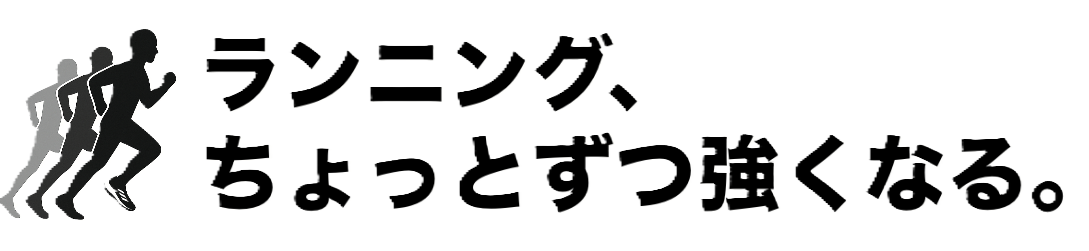レース2か月前の調整期──リディアード式「コーディネーション期」の実践法
【導入文】
マラソンまで残り約2か月。ロング走も重ねて、スピード刺激も入ってきた。
身体は確実に仕上がりつつある──でも、ここで気を抜くわけにはいきません。
リディアードのトレーニングでは、インターバル期の次に「コーディネーション期(調整と統合のフェーズ)」がやってくる。
このフェーズの目的は、「積み上げた力をまとめあげ、実戦に最適化する」こと。
- 走力
- スピード
- スタミナ
- フォーム
- リズム
それぞれを“バラバラに鍛えてきた”この4か月を、「レース仕様」に整えていく期間です。
今回は、リディアード式トレーニングのフェーズ4:コーディネーション期について、
- 理論的な背景
- 市民ランナーとしての実践法
- 優先度に応じたおすすめメニュー
を、実体験を交えて紹介します。
【理論編】“鍛える”から“整える”へ──スピード×スタミナ×効率を統合する
リディアードが提唱する「コーディネーション期」の役割はシンプル。
これまでバラバラに鍛えてきた能力を、レースで発揮できるようにつなげる。
✅ 具体的にはどんな目的?
- レースペースに身体を慣らす(神経系やフォーム、呼吸を最適化)
- 脚へのダメージや疲労を残さず、スピード刺激は保つ
- フォームやリズムを崩さず、動きの“感覚”を整える
- スタミナとスピードのバランスを最適化する
「この時期に無理に追い込まない」のが大前提。
過去の練習で作った力を“引き出す”フェーズです。
【トレーニング編】僕がやってよかった、コーディネーション期のメニュー
コーディネーション期の練習は、「何をやるか」より「どうやるか」が大切。
すべてのメニューにおいて、
- 疲労を残さない
- リズムとフォームを崩さない
- 終わった後に“いい感覚”が残る
- レースペース走は最長で21㎞まで
- 30㎞ロング走はレースペース+10秒/㎞より速く走らない
ことを重視しています。
✅ 僕が取り入れたメニュー(優先度別)
優先度①:レースペース走(16km)
- マラソンの本番ペースで“淡々と走る”練習。
- 僕は16kmを設定し、週1で行いました。
- 心肺・フォーム・呼吸など、すべてを本番モードに切り替えるスイッチ。
- 終盤の余裕度・脚の残り具合などもチェックポイント。
優先度②:30kmロング走(ペース段階式)
- 長い距離でペースの“コントロール力”と“粘り”を鍛える。
- 僕は以下のように、段階的にペースを上げていく方法を取り入れました:
- 前半10km:マラソンペース+30秒
- 中盤10km:マラソンペース+20秒
- 後半10km:マラソンペース+10秒
- ダメージを残さずに、レース後半を意識した粘りの脚づくりを狙います。
優先度③:テンポ走(5〜8km)
- ややキツめのペースで、余裕度と集中力を養います。
- 目安は「マラソンペース−10〜15秒/km」。
- 短時間でスピードとリズムを刺激し、レース前の“シャキッと感”をキープ。
優先度④:50/50シャープナー
- 50m全力+50mジョグを繰り返す、リディアード式のスピード刺激。
- 合計で約2km前後。
- 全力スプリントで神経系と速筋を目覚めさせ、回復を阻害せずに無酸素能力を維持できます。
- 僕は週1回、軽めのジョグ後にサクッと入れました。
【まとめ】
- コーディネーション期は、「鍛える」から「整える」への移行フェーズ。
- 過去の努力をつなぎ、“本番で使える力”に最適化する期間です。
- 疲労を残さず、感覚重視のトレーニングを中心に行いましょう。
「自分のレースペースが分からない」「練習メニューの組み方に不安がある」
そんな方は、お気軽にInstagram(@ichiro_42.195)のDMや、お問い合わせフォームからご相談ください!
レースまでの仕上げ、悔いなく準備しましょう。
次回は、最終フェーズ「テーパリング期」。
疲労を抜きながら、ピークを引き出すラスト数週間の戦略についてお話ししていきます。